近年、美術館・博物館の展覧会の広報を担当するPR会社が増加している。テレビやラジオ、ウェブ、SNS向けのプロモーション、プレスや関係者向けの内覧会、音声ガイドの対応など、PR会社の仕事は多岐にわたる。しかし、展覧会広報という仕事が生まれたのはここ20年程度のことである。
展覧会広報の黎明期からその仕事を請け負ってきた株式会社TMオフィス【※1】の馬場大輔(ばんばだいすけ)さんに、展覧会広報をはじめた経緯と現在、今後の展開についてお聞きした。

幼少期からアートに関心はあったのだろうか?
「実は幼い頃は、美術には全く関心がなかったんですよ。ただ、私の父が自由業で……ちょっと特殊な環境で育ったと思います。父はラジオのパーソナリティでもあった馬場章夫で、MBSで『ごめんやす馬場章夫です』というラジオ番組をしていました。父は、昼の12時までラジオ放送をしてから、その後に自分で取材をして、翌日にまたラジオで話すという珍しいスタイルだったので、早く帰ってくることもあれば、かなり遅いこともありました。取材先は関西近郊が多かったのですが、それこそどこかの博物館に行ったり、水が好きなので名水百選の場所に行ったり、山に登ったり……。実はラジオでそういうコンセプトでやっている人は少なかったんで、画期的だったようです。」

毎日放送ラジオ(MBSラジオ)のラジオ番組『ごめんやす馬場章夫です』は、月曜日から金曜日までの帯番組で1972年から2003年まで31年間放送された長寿番組であり、当時最多担当回数記録を打ち立てた(後に浜村淳の番組に更新される)馬場章夫は、京都市立芸術大学で日本画を専攻したが、在学中から探検部を結成し、当時の日本人ではあまり行かない、アフリカやミクロネシアの奥地などを探訪していた。



「土日は休みだったんですけど、月曜日にはまた取材で行ったところについて話さないといけないので、プライベートも家族旅行も同じなんですよね。小学校の頃に初めて海外旅行に行ったんですが、ハワイとかグアム、パリとか一般的な観光旅行とは違ったんです。基本的にはネタを探す旅行で、家族旅行もその一環でした。ちょうど10歳くらいの時に天安門事件が起きて、安くなるから旅行に行こうということで中国に行ったんです(苦笑)。それで天安門広場を車で通ったり、雲南省の少数民族のナシ族に会うため、世界遺産にもなっている虎跳渓(とらとびきょう)に家族で行ったりしました。そんなところに誰も日本の家族が来ることはないので、かなり珍しがられてテレビ局にも取材されたんです(笑)。あと、南アフリカやケニア、ザンビア、ジンバブエなんかにも行きました。もちろん直行便はないので、イギリスのヒースロー空港経由で何十時間もかかりました。野生のカバとかゾウ、サイ、ライオンなんかも見たわけなんです。当時、同級生でそんなところに行っている人は誰もいないから、特殊な家庭だったと思いますが貴重な経験だったと思います。」
馬場章夫は日本画専攻だったこともあったので、旅行時にスケッチなどもしていたのだろうか?
「父と旅行をしていて、彼が創作的なことをしているのは見たことがありませんね(笑)。目的としては完全にラジオのネタ探しですね。父はアーティスト活動は一切してないです。」
馬場の母は中学校の家庭科の教師で、ラジオ番組の企画などもあって3回も披露宴をしたという。馬場章夫の生活はすべてが番組のネタ元だったといえるかもしれない。
父親と同じような仕事に憧れたりしなかったのだろうか?
「父は自分の興味のある物事になんでも飛びついて、子供の頃からとんでもない行動力だなと思っていました。同じことをするのは無理だけど、裏方ならできるのでは......と思っていました。父の影響を受けてマスコミ業界には行きたかったけど、話すのが得意ではないため、裏方の方が合っているなと思いました。茶屋町のMBSのスタジオにも何度も収録を見に行きましたね。」
そこでマスコミのことを勉強するために大阪芸術大学に進学する。
「マスコミ業界に入りたかったんですが、全然人生設計してなかったんですよ(笑)。何となく食べていけたらいいか、くらいに考えていて。今考えたら父親の名前を使ったらどこかに入れたかもしれませんが、信条に反するから当時は嫌でしたね。コネを使って入っても後で苦労するんじゃないかとも思いましたし......。それで、当時アルバイト情報誌の『FromA』を見ていたら、今勤めているTMオフィスがアルバイトを募集していて、そこでアルバイトをすることになりました。」
株式会社TMオフィスは実業家でPR専門家の殿村美樹が、1992年に設立した会社で、いち早く地方自治体のPRを手掛けてきた。関西を中心に全国各地の地方自治体のPRを手掛け、実績を積んできた。例えば、びわこビジターズビューロー(滋賀県観光連盟)【※2】と組んで一緒にプレスツアーやメディアプロモーションなどを行っていた。他にも殿村は、「今年の漢字」「ひこにゃん」「うどん県」「佐世保バーガー」など、誰もが知っている地方発のプロモーションを数多く手掛け、多くの人々に知られるようになり、テレビやラジオにも出演し、現在では省庁の委員やアドバイザリーも務めている。
2016年には、殿村は自身のPRの経験を『ブームをつくる 人がみずから動く仕組み』(集英社新書)にまとめている。彼女によると、PRとは、パブリック・リレーションズの略であり、「多くの人に知らせて、社会的に好ましい信頼を得る」という意味があるが、「人が自ら動く仕組みづくり」を目標にしているという。つまり潤沢な予算を使った「広告」ではなく、まわりの空気を変えることで、自ら行動を起こすように促すものとして自身のPRを定義しているのだ。また、「PRを通じて永続的な文化をつくる」という高い志を掲げており、一過性のブームではなく、インターネットやブログ、SNSなどを含むボトムアップ的な発信から起こるムーブメントになることをいち早く重視してきた。馬場は、TMオフィスにアルバイトとして入社し、殿村の薫陶を受けて、地方自治体へのPR業務などに携わった。
「その時やっていたのは自社でPRしたクライアントの記事が新聞や雑誌に掲載されたら、カッターで切り取って台紙に張ったり、こういう面白い話があるから取材してほしい、と、マスコミの担当者を調べてお願いしたり、そういう仕事をしていました。」
しかし、マスコミの夢を諦められず退職して、就職活動を行うことになる。
「そうした仕事をするなかで、マスコミに入りたいという夢がまだ頭の片隅にあり、特に制作をやりたいなと思って、アルバイト自体は3、4年ぐらいして退職してるんです。全国のテレビ局や制作会社に履歴書を送りまくって、全国各地に面接にも出向いたんですけど、就職氷河期ということもあったのか箸にも棒にも掛からなかったですね(苦笑)。このままではあかんなと思って、殿村社長にお話ししたら、暖かく迎えてくれてTMオフィスで正社員として雇っていただけることになりました。」
そのうち小泉内閣の地方分権のための「三位一体改革」が進み、地方自治体の財源が増えた結果、地方にもお金が流れるようになったという。
「我々が、地方自治体の観光PR、シティプロモーション、移住定住促進などを一手に引き受けていましたが、大手のPR会社も地方自治体のPR業務にも参入するようになってきました。それで、地方自治体のPR業務が取り合いになりレッドオーシャン化してきたという状況にありました。」
馬場がTMオフィスに戻ってから1年ほど過ぎた2006年、朝日新聞の大阪本社の事業部から、2007年に神戸市立博物館で開催を企画していた「大英博物館 ミイラと古代エジプト展」のPR業務について突然、TMオフィスに問い合わせがあったという。
「当時、新聞社が手掛ける展覧会は、主に自社でメディアプロモーションをするわけなんですが、それだけでは広報が足らなくなってくるんです。ただ、同業他社に掲載してくださいとは言いにくい。それで他の新聞社にも掲載してもらったり、取材にきてもらえるような戦略を一緒に考えてほしいという依頼だったんです。それ以降、PR会社のようなところが主体となって、様々なメディアにプロモーションをするということにシフトしていくんですね。その先駆けにあたると思います。結果的に、「大英博物館 ミイラと古代エジプト展」は大成功だったこともあり、弊社も展覧会の広報事業が主になっていきました。我々よりも早くこのようなPR業務をやっていた企業があるかわからないですが、いずれにせよここ20年くらいの歴史になります。」


展覧会のPR業務というのは主にどのようなものがあるのだろうか?
「もちろん事前の話し合いによって変わるのですが、メディアに対するプロモーション、内覧会の受付、音声ガイド、最近ではインフルエンサーへの広報戦略などもやることもあります。」
どのようなことで広報効果の実績が図られるのだろうか?
「広告換算料金というのがあります。例えば、新聞の広告枠分がいくらという広告料金がありますので、掲載された記事の枠の大きさを広告料金に換算すると、その価値がいくらか算出できます。だから実際かけた料金の10倍以上の広告換算料金を保証するというようなお約束をしたりします。それくらいのリスクをとって保証をしないと、委託する側もメリットがありませんので……。ただ、最近は広告料金自体が下がっているので、何媒体以上は掲載する、とか全国のこことここには、必ず提案するなどしています。その中で、広報戦略のヒットといえるようなものは、やはりNHKの『日曜美術館』や、テレビ東京『新美の巨人たち』などに取り上げられるということがあります。やはりテレビの露出で大きく動員数が変わることがあります。」
しかし、近年はテレビの効果だけでは難しくなってきているという。
「コロナ禍を経て大きく変わったと言えると思います。美術館の展覧会は、コロナ禍以前は、40代~50代以上の固定のファンがいて、そこへはマスメディアで訴求が可能なんですよ。しかし、50代以上、60代、70代の人たちがコロナ禍をきっかけに、美術館・博物館に来なくなったんです。これは数値として顕著に表れているんです。今まではその人たちをターゲティングすればよかったんです。しかし、目標人数を達成するには、それだけでは難しく、上積みが必要ということもあり、主催者は若年層に目を付けるのです。しかし、昨今は若年層のマスコミ離れも目立ちます。そのため、インフルエンサーやオピニオンリーダーを積極的に活用するなど、若年層の行動を喚起するプロモーションが重要です。」
具体的にはどのようなプロモーションになるのだろうか?
「今までは、展覧会の魅力自体を伝えていればよかったんですが、それ以外の情報、例えば音声ガイドとかグッズ、コラボカフェ・グルメとか、若年層を狙った企画であることが多いです。人気の声優さんを使うとか……。展覧会と声優ファンは親和性が高いゾーンなんです。そのため、音声ガイドには声優が多いんです。そういう背景もあって、展覧会広報も昔とは違って多岐にわたるので大変です。後は多言語にして、インバウンドをどれだけ呼び込めるかということも課題になっています。」

インフルエンサーによる効果はどのようなものになるのだろうか?
「弊社が手掛けた例として、最近、国立京都国際会館で「京都 大恐竜博 ~動く!吠える!暴れる!」という展覧会のプロモーションをしまして。会期がわずか8月10日から17日までしかなかったのです。ネット媒体中心にマスメディアに掲載してもらったんですけど、それ以外に内覧会に小学校のお子さんがいるお母さんのインフルエンサーをお呼びしました。そうしたら恐竜が動いている様子とか子供が遊んでいる様子とかを30秒とか1分の動画にまとめてインスタグラムにあげてくれるんですけど、すごくうまいんですね。あるインフルエンサーの動画が80万とか90万回くらい再生されたんです。そしたらものすごい勢いで広がって、具体的な人数はわからないんですけど当初想定していたより明らかに家族連れが増えたんですね。だから、今までのようにテレビやラジオといったマスメディアを通じて来られるお客様と、SNSを通じて来られるお客様はかなり違うので、二分化しているといえるかもしれません。」
近年、TMオフィスのPRではないが、関西圏でも京都市京セラ美術館で開催した「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」展や「蜷川実花展 with EiM:彼岸の光、此岸の影」展、大阪中之島美術館で開催したルイ・ヴィトン「ビジョナリー・ジャーニー」展のように、明らかにSNSの効果で動員される例が増えている。今後の美術館の展覧会にとってPR業務とはどのようなものになると思うのだろうか?
「従来ならマスメディアだけやっていればよかったわけですが、これからは若年層やインバウンドをいかに集客するかという視点で考えないといけないと思いますね。」
馬場は働きながら京都芸術大学の通信教育部で学芸員資格も取得している【※3】。なぜ社会人になってから直接的に業務に関係のない学芸員資格を取得しようと思ったのだろうか?
「PR業を手掛けるうえでの必要な資格は特に無いのです。だから展覧会広報と言っても、PR業務を担当している人たちで、学芸員資格を持っている人は少ないんです。私は展覧会広報を極めようと思ったので、国家資格である学芸員資格が必要だと感じました。また、クライアントである美術館・博物館もその方が安心するに違いないですし、何より自分の経歴をアピールしやすいんです。」
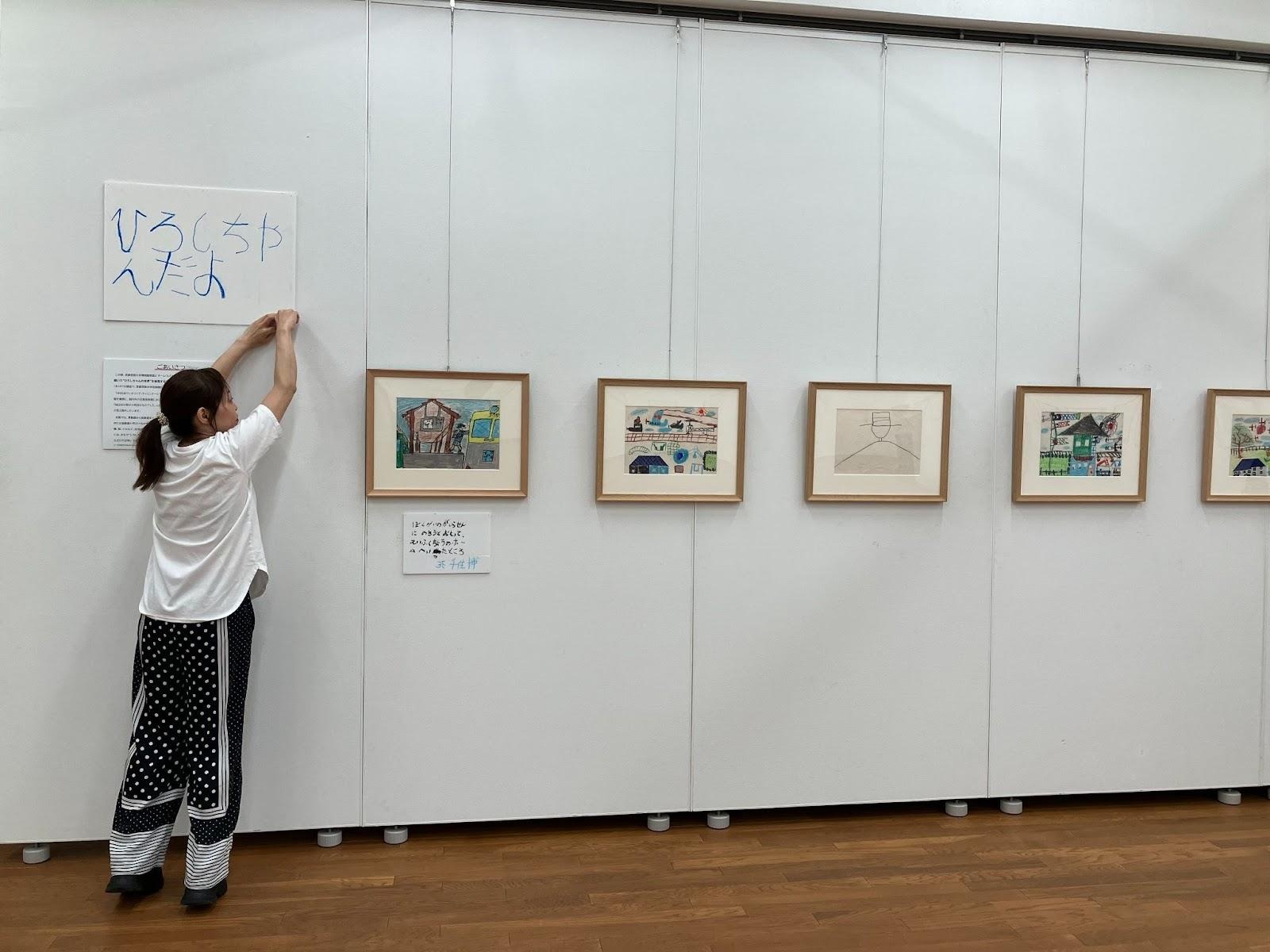
実際、社会人をしながら学んでみてどうだったのだろうか?
「楽しかったですよ(笑)。ただ、レポートが本当に大変で(苦笑)、土日しか時間がないわけですが、土日もイベントがあると集中できないし、レポートは本当に集中しないと書けないなと思いました。博物館の実習では平日に行かないといけないこともありましたし。」
学芸員資格をとって変わったことはあったのだろうか??
「感覚的なことかもしれませんが、美術館・博物館や、展覧会を企画するマスコミの事業部からの私を見る目は変わったように思います。PR会社の立場上、展覧会の広報ミーティングにしか呼ばれることしかなかったのですが、最近は全体会議にも顔を出させていただくことが増えました。学芸員の資格を持っている広報パーソンなので、広報関係だけじゃなくて、展覧会の根底の部分から客観的な視点で見ることができるんじゃないかと認めてもらっているような気がします。」
内部に入ってみて感じることはどういうことだろうか?
「展覧会の広報は、学芸員の方が担うこともあるんですが、やはり企画している内部の人間だと見えないこともよくあるんですよね。だから我々のような外部の人間が、客観的な視点から広報戦略を組むことで、多くの人に展覧会の魅力を届けることができると確信しています。」
現在では多くの展覧会広報の事業者が生まれているがそれについてはどう思うのだろうか?
「コロナ禍以降、関西の展覧会は激減していましたが、今ではコロナ以前のように活性化してきました。弊社だけで全ての展覧会のPR業務を担うことはできませんし、共存共栄できるのではないかと思います。弊社は、PR業界の中では創業36年と歴史があり、会社にもブランド力があります。殿村が、自治体PRや文化PRを手掛けることによって、ブランドを築いてきました。「信用」はビジネスを行う上で非常に重要で、私が例え一人で会社を起こしたとしても、「信用」が無いため、展覧会の仕事は担当できないと思います。会社には、非常に感謝しています。」
父の影響もあって、メディアの制作をするのが目標であったが、現在はこれが天職と思っているのだろうか?
「そうですね。展覧会のPR業務にはやりがいを感じていますし、天職といえると思います。例えばテレビ制作会社の方から、仕事についてお話を聞いたりすることはありますが、かなり大変な仕事であることは間違いないですし。結果的ではありますが、この仕事をするようになってよかったと思います。芸術に興味が湧いてきたこともありますので、もっと発信していきたいと思います。」
最後に、これから展覧会のPR業務をしたいという人たちへのアドバイスをうかがった。
「PR会社は、映画の影響もあり、華やかに見えることがあるかもしれません。しかし、やっていることは極めて地味です。クライアントとの折衝や、記者への提案、画像貸出や原稿のチェックなど、いかに展覧会の話題を社会に狙い通りに発信できるかが重要な仕事です。ただ、時代が急速に変わっているので、柔軟性があること、客観的な視点を持っていることが広報パーソンにとっては必要な資質になります。あと、AIの発展が目覚ましい昨今ですが、広報・PRの仕事は、結局、人対人のコミュニケーションビジネスなので、取って代わられることはありません。とにかく頭を使う仕事なので、ボケ防止にもなりますよ (笑)。」
-----------------------
【※1】株式会社TMオフィス
【※2】びわこビジターズビューロー
【※3】京都芸術大学通信教育部 科目等履修(博物館学芸員課程)
(上記URLは全て2025年10月14日に最終閲覧)
-----------------------
株式会社TMオフィス 執行役員 チーフPRディレクター、博物館学芸員
公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会関西幹事
一般社団法人地方PR機構 上席主任研究員。
TMオフィスは、「今年の漢字」や「うどん県」など地方発国民的ブームのPRを手掛けるとともに、2006年頃からは、国内外の貴重な芸術文化を披露する展覧会のPRを追及。2024年時点で、累積実績数1500件を突破する。2025年3月、博物館学芸員資格を取得。滋賀県「国スポ」「障スポ」広報・県民運動専門委員(2019年~)、大阪市天王寺区広報紙、大阪市阿倍野区広報紙などの企画編集業務委託 選定委員を務める。
文筆家、編集者、色彩研究者、美術評論家、ソフトウェアプランナーほか。アート&ブックレビューサイトeTOKI共同発行人。独自のイメージ研究を基に、現代アート・建築・写真・色彩・音楽などのジャンル、書籍・空間・ソフトウェアなどメディアを横断した著述・編集を行なっている。美術評論家連盟会員、日本色彩学会会員。